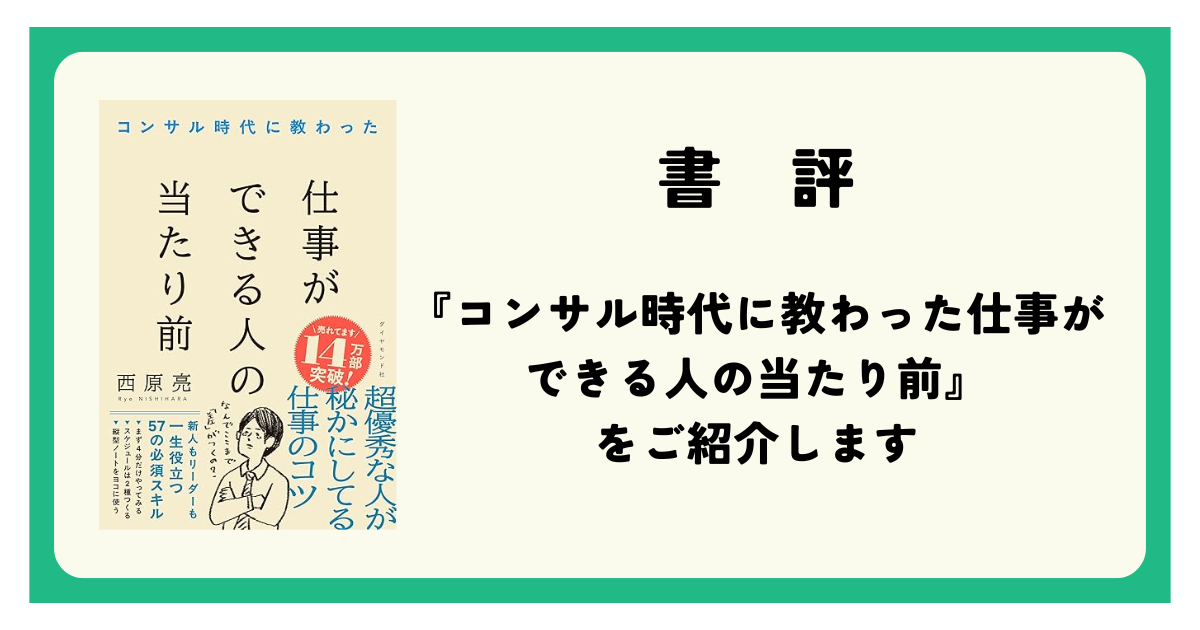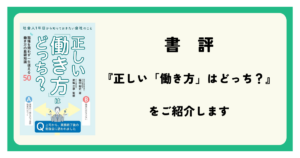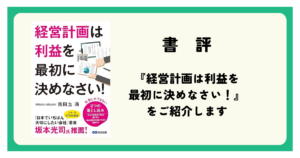赤城 正孝
赤城 正孝みなさま、こんにちは。中小企業診断士の赤城正孝です。
当サイトの書評では、各書籍から特に重要な考えを一つ取り上げ、実践方法や成功例を交えながら、中小企業の成長につながる気づきを発信しています。
本日は、こちらの一冊を取り上げます。
書籍情報
書籍名: コンサル時代に教わった仕事ができる人の当たり前
著者名: 西原 亮
ジャンル: 人材育成
著者の西原さんは、「にっしー社長」としてYoutubeやTikTokでビジネススキルに関する情報発信をされていらっしゃいます。
そんな「にっしー社長」の初の著書が本著です。
書籍概要
本書は、仕事を行う上での考え方やコミュニケーション等の実行方法について解説しており、主に若手社員向けの書籍と言えるでしょう。
しかし、人材育成に悩む社長にとっても有益な情報が記されています。
特に印象的なのは、「実行できる単位まで分解する」という章です。
上司から「来年度の新卒採用プランを考えて」と指示を受けた場合、経験の浅い社員は、何をどこまで行えば良いのか分からず、途方に暮れてしまうかもしれません。
本書では、ゴールを明確にして上司と認識を合わせるなどの解決方法が提示されていますが、私は、指示を出す側である社長の視点も重要だと考えます。
指示を「分解」し、従業員の成長を促す
従業員は皆、本書に登場するような「仕事ができる人」ではありません。
中小企業の社長が従業員に指示を出す際、指示が大きすぎて従業員が理解できないケースは多々あります。
「来年度の新卒採用プランを考えて」という指示も、その一例でしょう。
このような場合、従業員が闇雲に仕事を始めてしまうと、非効率なばかりか、重大な漏れが発生する可能性もあります。
社長は、まず指示内容を「従業員が実行できる単位まで分解」し、従業員と認識を合わせることが重要です。
例えば、「新卒採用プラン」であれば、
- 現在の採用状況の分析
- 来年度の採用目標人数の設定
- 採用ターゲットの明確化
- 採用手法の選定
- 採用予算の策定
- スケジュール作成
など、より具体的なタスクに分解することができます。
そのうえで、分解したタスクを従業員自身にさらに細かく分解させるようにしましょう。
従業員の成長を促すためには、仕事の粒度が大きすぎても小さすぎても良くありません。
指示を出す際のポイントは、従業員の少し背伸びすれば届くレベルの仕事を指示することです。
指示を「分解」することのメリット
- 従業員の理解度と社長の期待値のギャップを把握できる。
- ギャップが解消されれば、従業員は一人で業務を遂行できるようになる。
- 従業員の調べる、考える時間が削減でき、業務効率化につながる。
すぐにできるアクションプラン
- 従業員に業務の全体像を伝え、理解度を確認しましょう。
- 従業員自身にタスクを分解させ、どこまで分解できるか確認しましょう。
- 分解したタスクをさらに細かく分解し、従業員に指示を出してみましょう。
まとめ:本書を活用し、人材育成と業務効率化を実現しよう
本書は、若手社員だけでなく、社長自身も「仕事ができる人」になるためのヒントを与えてくれます。
本書で紹介されている考え方を実践することで、従業員の主体性を育み、人材育成と業務効率化の両立を実現できるでしょう。
ぜひ本書を手に取り、あなたの企業の人材育成に役立ててください。